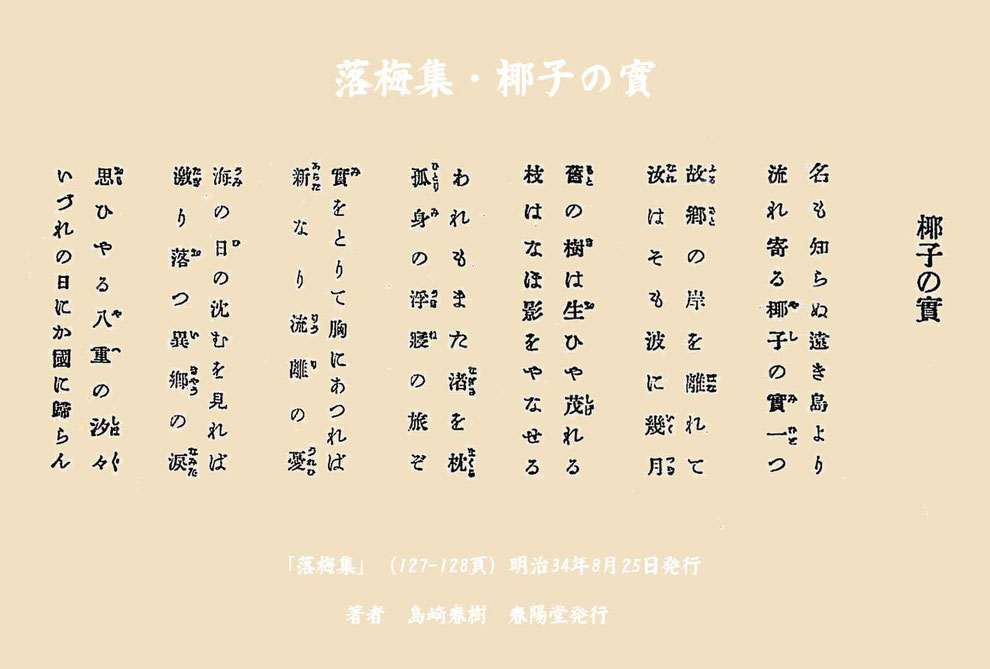
柳田国男が島崎藤村へ「椰子に實」の話をしたことが書かれている「朝日選書7・故郷七十年」と「海上の道」より抜粋して下記に紹介する。
藤村の詩「椰子の實」柳田国男
僕が二十一のころだつたか、まだ親が生きているうちじゃなかつたかと思う。少し体を悪くして三河に行って、渥美半島の突つ端の伊良湖岬に一ヶ月靜養していたことがある。
海岸を散歩すると、椰子(やし)の實が流れて来るのを見つけることがある。暴風のあつた翌朝などことにそれが多い。椰子の實と、それから藻玉(もだま)といつて、長さ一尺五寸も二尺もある大きな豆が一つの莢に繋つて漂着して居る。シナ人がよく人間は指から老人になるものだといつて、指先きでいじり廻して、老衰を防ぐ方法にするが、あれが藻玉の一つなわけだ。それが伊良湖岬へ、南の海の果てから流れて来る。ことに椰子の流れて来るのはじつに嬉しかつた。一つは壞れて流れて来たが、一つの方はそのまま完全な姿で流れついて来た。
東京へ帰ってから、そのころ島崎藤村が近所に住んでたものだから、帰って来るなり直ぐ私はその話をした。そしたら「君、その話を僕にくれ給えよ、誰にもいわずにくれ給え」ということになつた。明治二十八年か九年か、一寸はつきりしないが、まが大学に居るころだつた。(す)るとそれが、非常に吟じやすい歌になつて、島崎君の新体詩というと、必ずそれが人の口の端に上るというようなことになつてしまつた。
この間も若山牧水の一番好いお弟子の大悟法(だいごぼふ)君といふのがやつて來て、「あんたが藤村に話してやつたつて本当ですか」と聞くものだから、初めてこの昔話を発表したわけであつた。
(中略)
藤村の伝記を見ても判るように、三河の伊良湖岬へ行つた気遣いはないのに、どうして彼は「そをとりて胸にあつれば」などという椰子の実の歌ができたのかと、不思議に思う人も多からう。全くのフィクションによるもので、今だからいうが真相はこんな風なものだつた。もう島崎君も死んで何年にもなるから話しておいてもよからう。この間も発表して放送の席を賑わしたことである。いずれにしてもこれは古い話である。
参考(「故郷七十年」柳田国男 朝日選書7 188~189頁より)
柳田国男「海上の道」六、七より
途方もなく古い話だが、私は明治三十年の夏、まだ大学の二年生の休みに、三河みかわの伊良湖崎いらござきの突端に一月余り遊んでいて・・・・・、(中略)
今でも明らかに記憶するのは、この小山の裾すそを東へまはつて、東おもての小松原の外に、舟の出入りにはあまり使はれない四、五町ほどの砂浜が、東やや南に面して開けていたが、そこには風のやや強かつた次の朝などに、椰子やしの実みの流れ寄っていたのを、三度まで見たことがある。一度は割れて真白な果肉の露あらはれ居るもの、他の二つは皮に包まれたもので、どの辺の沖の小島から海に泛うかんだものかは今でも判わからぬが、ともかくも遥かな波路なみじを越えて、まだ新らしい姿で斯こんな浜辺まで、渡つてきていることが私には大きな驚きであった。
この話を東京に還かえつてきて、島崎藤村とうそん君にしたことが私にはよい記念である。今でも多くの若い人たちに愛誦あいしょうせられている「椰子の実」の歌といふのは、多分は同じ年のうちの製作であり、あれを貰もらいましたよと、自分でも言はれたことがある。
そを取りて胸に当あつれば
新あらたなり流離の愁うれひ
(中略)椰子の実の流れ着くという浜辺は多かったはずであるが、是が島崎氏のいうような遊子ゆうしによって、取り上げられる場合が少なかったかと思われる。昔はこの物を酒杯に造つて、珍重する風習があり、それも大陸から伝はつて来た様に、多くの物知りには考へられて居た。
(後述略)
余談だが、現在も固い椰子の実は色々と加工され様々な「器」として使用されている。
下の画像は椰子の実の「掛花入」である。

